こんにちはおさるです。
私は大阪市内で働く不動産屋です。
売買仲介の仕事をしていると、売買契約書の作成などにおいて土地建物の比率について算出しなければいけません。
今日は土地建物の比率についてどうやって算出しているか解説していきたいと思います。
土地建物の算出がいる理由
そもそも何故土地建物の比率が必要なのかという点についてです。
結論、消費税と減価償却(譲渡所得)を算出するため土地建物の比率を出さなければいけません。
消費税に関しては、一般個人の方や免税事業者の方はほとんど関係のない話で、対象となるのは課税事業者です。
減価償却については個人でも法人でも不動産を購入するなら関わってくる部分です。
それぞれ解説していきたいと思います。
土地建物の算出がいる理由①消費税
土地は消費しないものとして非課税です。
建物は消費するものとして消費税がかかります。
個人が自分の居住用として物件を購入する際に関しては特に気にしないことではありますが、例えば課税業者が物件を売る場合などは影響があります。
物件を売却した際に消費税を多くもらえば(建物比率が高い場合)その分納税する額も大きくなります。
課税業者の売主としてはできるだけ建物比率は低く消費税は少ない方が嬉しいということです。
土地建物の算出がいる場合②減価償却
不動産の建物部分については減価償却という会計処理をすることができます。
減価償却というのは建物の購入金額を一度で経費計上せず、複数年に分けて少しずつ経費を計上することを言います。
例えば建物価格1000万円・償却期間10年の場合、購入年に1000万円経費とするのではなく100万円を10年に分けて経費として計上するということです。
土地と建物のそれぞれの金額を出しておかないと、建物部分の減価償却も計算できないので算出が必要になるということです。
知らない人に向けて簡単に解説すると、減価償却には次の2つのポイントがあります。
- 減価償却期間中は経費を計上できているので節税になる
- 売却時は減価償却で経費化された分(簿価)を元に譲渡所得税を決定する。
1の減価償却期間中に節税になるというのはイメージしやすいと思います。
先程の例で言うと毎年100万円を経費として計上することができるので、個人の場合は給与所得・法人の場合は法人税の課税対象の金額が少なくなって、結果として税金が安くなります。
2の譲渡所得税については、売却時の話です。
売却時は売却によって利益が出た分に対して税金がかかります。
この利益というのは、実際に買った金額と実際に売れた金額ではありません。
帳簿上の価格と実際に売れた金額の差額に対して利益がかかります。
帳簿上の価格というのは減価償却が考慮された金額で、1000万円の建物を購入して100万円×5年所有した場合、その建物価格は帳簿上500万円です。
仮に700万円で売れたとしたら実際には300万円のマイナスですが、帳簿上200万円利益が出たと言うことになり譲渡所得税が発生します。
少し複雑な内容ですが減価償却というのは少し変わった会計のルールで、不動産とは切っても切り離されずかなり奥深いテーマです。
土地建物の比率の算出方法
一般的に物件資料には「物件価格〇〇万円」のみ書かれていて内訳の記載はありません。
なので私たち不動産業者が売買契約書など作成の際に、物件価格から比率を算出して内訳を明記します。
土地建物の比率を算出するには次の4つの方法があります。
- 消費税額から判断する
- 固定資産税評価額の比率で計算する
- 土地、建物の原価を基に計算する
- 不動産鑑定士に依頼する
原則として、土地建物の比率は「絶対にこれ!」というやり方は決まっていないです。
上記のいずれかの方法で根拠を明確にできるようにさえしておけば、税額のトラブルなどには発展しないで済みます。
ただし、消費税額が変動することから売主は消費税が低い方が納税額が少なくて済む、買主は消費税が高い方が減価償却を大きくとれるという利益が相反する形になるのでお互いが納得できる比率でするのが大事でしょう。
消費税額から判断する
まずは一番分かりやすい消費税額から判断する方法です。
土地は消費税がかからず、建物には消費税がかかります。
消費税が既に分かっているということであれば、逆算して建物価格を算出することができます。
2019年10月以降であれば消費税10%なので、仮に150万円が消費税額とすれば×11で建物価格の合計は1,650万円(建物価格1,500万円+消費税150万円)です。
あとは売買代金の合計から建物価格を差し引いた金額が土地の金額です。
固定資産税評価額の比率で計算する
私のような不動産仲介会社としては、固定資産税評価額から判断することが多いです。
役所で公課証明書を取得すれば土地建物の固定資産税評価額が分かります。
これらを元に比率を算出します。
.jpg)
.jpg)
※公課証明書・評価証明書・固定資産税評価額・固定資産税課税標準額について、用語など簡単な説明は別の記事でしています。
評価額を入力すると、自動で計算してくれるサイトもあったりします。こちら。
ぜひ参考にしてみてください。
土地、建物の原価を基に計算する
こちらの方法は、新築時の建物価格を計算して経過年数を考慮して金額を算出する方法です。
私自身この方法は使ったことありませんが、公課証明書を取得する手間がないという点と、建物価格が小さくなることが多く、消費税を低くできる・減価償却を少なくできるなどのメリットがあります。
- 新築時の建築費単価×建物面積で当時の建物費用を算出
- 経過年数分を減価償却する
- 売買価格から算出された建物価格を引いて土地価格を求める
ざっくり上記の流れでの計算で、少し複雑なので詳細はご自身でお調べいただくことをお勧めします。
不動産鑑定士に依頼する
一番確実な方法で堅実なのが不動産鑑定士に依頼することです。
こちらは不動産鑑定士に依頼して、鑑定評価額から土地建物の計算をします。
ただ不動産鑑定士に依頼するとなれば費用は発生してしまいます。
確実で合理性が高い方法ではありますが、費用と時間がかかることから実務ではあまり使われないと思います。

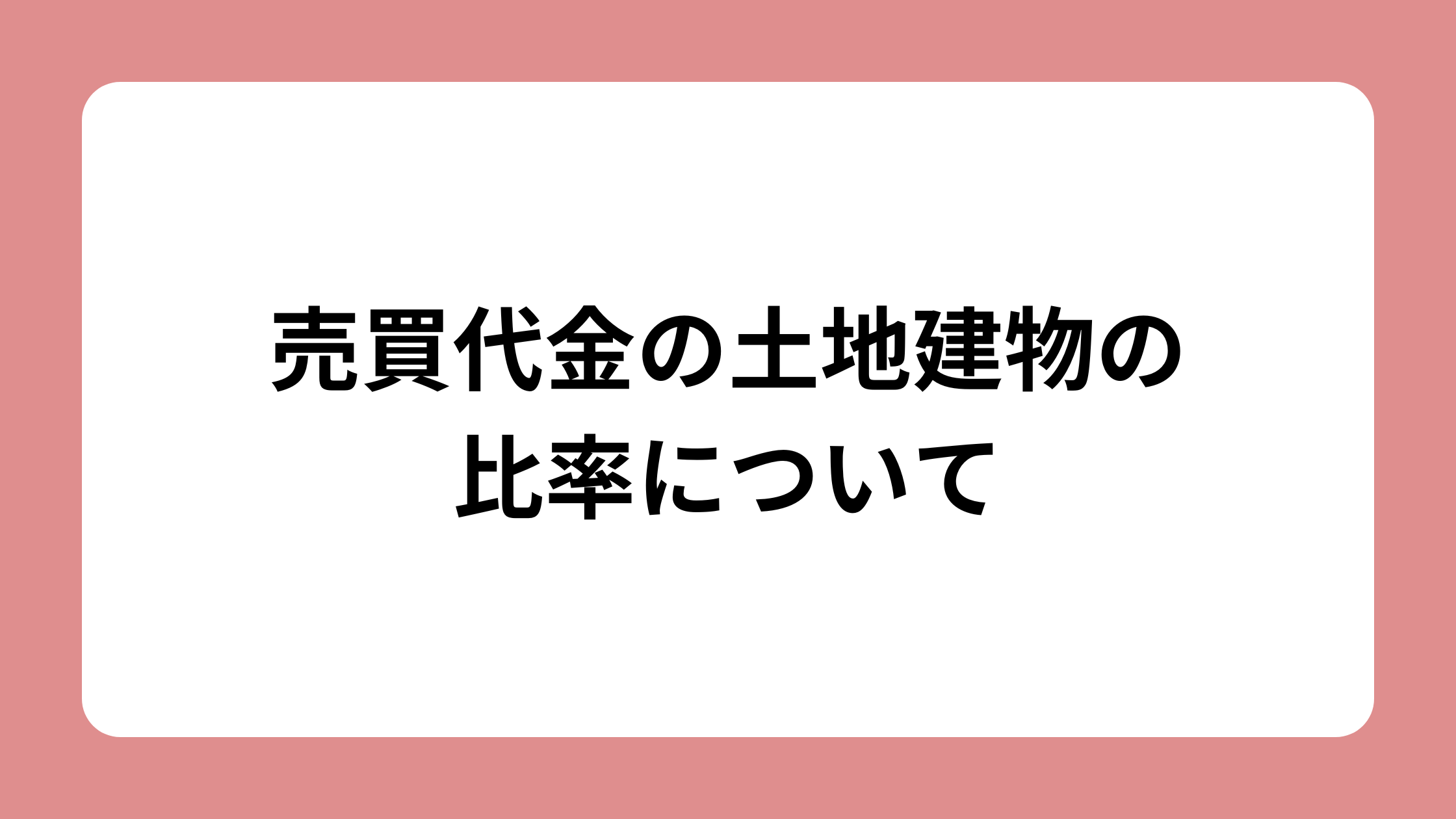

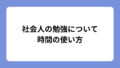
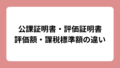
コメント